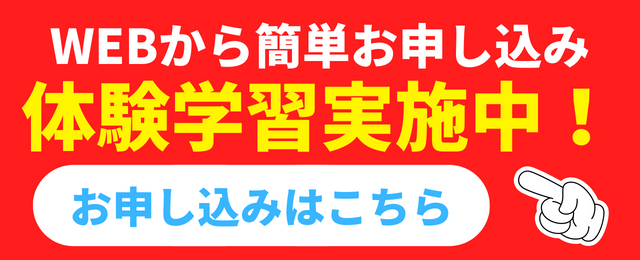― 早めの対策がカギになります ―
中高一貫校にお通いの保護者さまから、最近よくこんなご相談をいただきます。
「学校の進度が早すぎて、子どもがついていけていない気がする」
「特に数学と英語が苦手になってきたけど、今さら追いつけるのか心配…」
このように、一度つまずいてしまった教科を「取り戻す」には、想像以上の時間とエネルギーが必要です。
特に中高一貫校では、独自のカリキュラムで授業がどんどん進んでいくため、早めの気づきと対応が何よりも重要になります。
本記事では、中高一貫校における数学・英語の「取り戻し」に時間がかかる理由と、どうすれば効率よくリカバリーできるのかについて、詳しく解説していきます。
中高一貫校の授業進度は“とにかく早い”
中高一貫校では、一般の公立中学校・高校と比べて、次のようなカリキュラム上の特徴があります。
- 中3の段階で高校内容に突入する学校が多い
- 高1で数Ⅱ・Bや英文解釈を学ぶケースも
- 大学受験に向けて、実質“高2終了時点”で全範囲を終えることを目指すことも
つまり、他の学校よりも1〜1.5年早く高校内容に入っていくため、「ちょっとつまずいたから後で復習しよう」と放置していると、その間に学習内容がどんどん積み上がり、気づいた時には取り戻しが非常に困難になっているというケースが多く見られます。
数学は“積み重ね”が命。抜けた穴の補修には時間がかかる
数学は、前の単元の理解があってこそ、次の単元が理解できる教科です。たとえば、
- 正負の数 → 方程式 → 関数 → 図形 → 数学Ⅰ・A・Ⅱ・B …
といったように、すべてが「積み木」のようにつながっています。
したがって、一度つまずいてしまうと、
「過去の単元を復習しながら、今の授業にもついていく」
という“二重学習”が必要になり、その分、回復に時間がかかってしまいます。
また、定期テストで「一夜漬けで点が取れた」としても、理解の土台が固まっていなければ、模試や入試で応用が利かないという問題にもつながります。
英語も「感覚で読む」クセがついていると危険
英語も、数学と同様に積み重ねが必要な科目です。ところが、以下のような状態になっている生徒が少なくありません。
- 英単語の意味を「なんとなく」で覚えている
- 文法があいまいなまま長文を読むクセがついている
- 和訳が“それっぽく”できていても、構文理解ができていない
このような状態では、英語を読むスピードや精度が上がらず、大学入試レベルの英文には太刀打ちできません。
基礎からやり直す必要がある場合、「読み方のクセを直す」のに時間がかかるため、やはり英語もリカバリーには相当の根気が求められます。
取り戻すためにはどうすればよい?
中高一貫校の授業進度に追いつくためには、以下のような対策が有効です。
① 学習の“優先順位”を明確にする
苦手な単元を洗い出し、「どこから」「どこまで」取り戻すべきかを明確にすることが重要です。
② 週単位での学習計画を立てる
「今の授業のフォロー」+「過去単元の復習」を週単位でどう組み込むか、現実的なスケジュールを立てる必要があります。
③ 必要に応じて第三者の力を借りる
自力での復習に限界を感じる場合は、塾や家庭教師などのサポートを利用するのも一つの手です。特に中高一貫校のカリキュラムに精通した塾を選ぶことが大切です。
まとめ:早めの対応が“時間短縮”につながる
中高一貫校では、進度が早いからこそ、「あれ?ちょっと分からなくなってきたかも…」と感じたタイミングでの対処が非常に重要です。
取り戻すのに時間がかかるからこそ、気づいた今が、リスタートのチャンスです。
高木塾では、中高一貫校に通う生徒の特性に合わせた個別対応で、基礎の見直しから応用力の養成までをサポートしています。「今のままで大丈夫かな…」と少しでもご不安があれば、ぜひ一度ご相談ください。